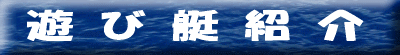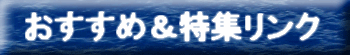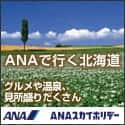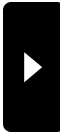2012年05月28日
トンネル工事爆発事故と施工計画書。
あ、これはマジメな記事なのでオチはないことを明記しときますがっ
くわえて、負傷された方へのお見舞いを申し上げるとともに亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
くわえて、負傷された方へのお見舞いを申し上げるとともに亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
先週起こった南魚沼八箇峠のトンネル工事現場での爆発事故。
実はあのあたりは魚野川に行くときも近くを通るし、3年前新潟上越の長期滞在のときにも現在の峠道の国道253号を利用していた(あとになって県道76号のほうが便利だからそっちにしたけど)。
場所的によく知っているから続報をみていたら、いろいろと確認しなきゃわからない点がでてきた。もちろんこれを書いた後にも新しい事実が出るかもしれないので、5月28日夕方時点で確認できた内容で見てみる。
まずは建設業法上の技術者等が機能していたのかという点。
報道では北陸地方整備局(新潟は国交省の管轄区分でいくと北陸整備局管内になる)は「ガスが出る可能性は口頭で伝えてあり、施工計画書にもガス対策について書いてあるので当然元請(佐藤工業)は知っていた」としている。
対して佐藤工業の担当者(担当者という書き方は新聞とか報道のレベルではまあ仕方がないけど、そのとき取材に応じた社員であり、もしかするとちゃんとわかってないヒトかもしれないという含みが残る)は「ガスが出るなんて聞いてなかった」
一次請の担当者も「ガスが出るなら防爆仕様の換気装置にしていた」
発注者(整備局)と受注者(佐藤工業及びその請負)の意見に食い違いが見られ、報道ではその両者の発言を載せているのだが…
整備局側が持ち出してきたのは「施工計画書」
受注して工期当初の定例会あたりでまず発注者への提出が求められる書類で、工事概要からはじまり工程管理、労働安全衛生管理、品質管理の方法、それに工法書やどういう法令に準拠するかを明記したりすることによって、工事全体が見えてくるもの。
この工事は金額は正確にはわからないが、監理技術者の専任が求められる規模であり、したがって佐藤工業の監理技術者が押印した正式な書類(実際にはダメ出しを食らうこともあるので、まず無印の案ベースで発注者に確認してもらうこともある。もちろん、正式版を早めに出せればいいのでそういう摺り寄せはアリ)となるわけで、工事上では「バイブル」
そこにガスに関して書かれていれば、発注者も受注者もガスに対して認識はあったことになり、佐藤工業の「担当者」の言い分にはまるっきり信頼性はなくなる。
ただし、この工事は当初ほくほく線のそばに約5000mのトンネルということで設計されたが、その位置でガス噴出のおそれがあったので、500mずらし、長さも約3000mで計画変更になったらしい。そのころの話は変更になったことしか出ていないのではっきりしないが、当初の5000m設計当時に工期が始まっていれば、施工計画書にはガスのことが書かれていて当たり前。
その後、3000mへの変更(位置的にも500m南に移動)が決まってからであれば、ガスは大丈夫だろうという認識になってもおかしくはない。
なので、整備局が持ち出した計画書はいつ時点の第何版なのかがわかればよりハッキリしてくる。
変更前の日付でありその当時の版を持ち出して言っているのであればそれは現況のことを示していないから「過去の」施工計画書であり、その後の版のみ有効ということになる。
変更後の施工計画書で正しく確認しても記述があるなら佐藤工業の「担当者」は現場代理人でも技術者でもない単なる社員が受け答えたとしか考えようがない。
まずガスの点では、整備局が持ち出した施工計画書が現行の版だとしたら佐藤工業も下請も現場代理人や技術者がまったく機能していなかったといってよい。
もし日付が古い計画書であれば、整備局も何か瑕疵があった可能性は否定できないが、それはおいおいわかるだろうから、施工計画書が意味することをわかっていただければよい。
次に、労働安全衛生上の主任者責任者等が機能していたかという点。
救助状況でわかったものも含めいくつか問題点がある。
可燃性のガス以前に酸欠をチェックしていたかということ。
報道では900m地点で酸素濃度は14%を切っていたという。
もちろん、可燃性のガスが爆発したのだから、その後では酸素濃度は極端に下がるに違いないんだが、本来換気できていない、全通もしていないトンネル(深い横穴)に入るには、手前から換気していき酸欠をチェックしながら奥に入っていくのが普通。1000mを超える長い上り勾配で行き止まりの穴であれば数日前から換気するくらい考慮するはず。くしくも救助の際、もっとも難航したのが換気であったわけだし。
また、こういう場所では酸欠だけとは限らないので混合検知ができるものを使用するにこしたことはない。
まず何よりも酸欠・硫化水素等作業主任者は置くべき現場であるし、主任者はその手順を踏んだのかがわからない。状況だけから言うと無防備に入っていったように思える。
下請関係も一緒に入っているところを考えると安全衛生責任者等も請負者間できちんと機能していたか不明。
それに中断工事の再開であれば災害防止協議会等を開催する、リスクアセスメントを見直す、などなど事前におこなうことが必要なんだけど…
…と、ここまで書いたけど。
今後事実が明らかになってくるだろうけど、私も業種は違うが監理技術者であり、酸欠・硫化水素作業主任者であり、職長/安全衛生責任者を教育するRSTという立場なので、今回の事故は決して他人事ではないと思う。
実はあのあたりは魚野川に行くときも近くを通るし、3年前新潟上越の長期滞在のときにも現在の峠道の国道253号を利用していた(あとになって県道76号のほうが便利だからそっちにしたけど)。
場所的によく知っているから続報をみていたら、いろいろと確認しなきゃわからない点がでてきた。もちろんこれを書いた後にも新しい事実が出るかもしれないので、5月28日夕方時点で確認できた内容で見てみる。
まずは建設業法上の技術者等が機能していたのかという点。
報道では北陸地方整備局(新潟は国交省の管轄区分でいくと北陸整備局管内になる)は「ガスが出る可能性は口頭で伝えてあり、施工計画書にもガス対策について書いてあるので当然元請(佐藤工業)は知っていた」としている。
対して佐藤工業の担当者(担当者という書き方は新聞とか報道のレベルではまあ仕方がないけど、そのとき取材に応じた社員であり、もしかするとちゃんとわかってないヒトかもしれないという含みが残る)は「ガスが出るなんて聞いてなかった」
一次請の担当者も「ガスが出るなら防爆仕様の換気装置にしていた」
発注者(整備局)と受注者(佐藤工業及びその請負)の意見に食い違いが見られ、報道ではその両者の発言を載せているのだが…
整備局側が持ち出してきたのは「施工計画書」
受注して工期当初の定例会あたりでまず発注者への提出が求められる書類で、工事概要からはじまり工程管理、労働安全衛生管理、品質管理の方法、それに工法書やどういう法令に準拠するかを明記したりすることによって、工事全体が見えてくるもの。
この工事は金額は正確にはわからないが、監理技術者の専任が求められる規模であり、したがって佐藤工業の監理技術者が押印した正式な書類(実際にはダメ出しを食らうこともあるので、まず無印の案ベースで発注者に確認してもらうこともある。もちろん、正式版を早めに出せればいいのでそういう摺り寄せはアリ)となるわけで、工事上では「バイブル」
そこにガスに関して書かれていれば、発注者も受注者もガスに対して認識はあったことになり、佐藤工業の「担当者」の言い分にはまるっきり信頼性はなくなる。
ただし、この工事は当初ほくほく線のそばに約5000mのトンネルということで設計されたが、その位置でガス噴出のおそれがあったので、500mずらし、長さも約3000mで計画変更になったらしい。そのころの話は変更になったことしか出ていないのではっきりしないが、当初の5000m設計当時に工期が始まっていれば、施工計画書にはガスのことが書かれていて当たり前。
その後、3000mへの変更(位置的にも500m南に移動)が決まってからであれば、ガスは大丈夫だろうという認識になってもおかしくはない。
なので、整備局が持ち出した計画書はいつ時点の第何版なのかがわかればよりハッキリしてくる。
変更前の日付でありその当時の版を持ち出して言っているのであればそれは現況のことを示していないから「過去の」施工計画書であり、その後の版のみ有効ということになる。
変更後の施工計画書で正しく確認しても記述があるなら佐藤工業の「担当者」は現場代理人でも技術者でもない単なる社員が受け答えたとしか考えようがない。
まずガスの点では、整備局が持ち出した施工計画書が現行の版だとしたら佐藤工業も下請も現場代理人や技術者がまったく機能していなかったといってよい。
もし日付が古い計画書であれば、整備局も何か瑕疵があった可能性は否定できないが、それはおいおいわかるだろうから、施工計画書が意味することをわかっていただければよい。
次に、労働安全衛生上の主任者責任者等が機能していたかという点。
救助状況でわかったものも含めいくつか問題点がある。
可燃性のガス以前に酸欠をチェックしていたかということ。
報道では900m地点で酸素濃度は14%を切っていたという。
もちろん、可燃性のガスが爆発したのだから、その後では酸素濃度は極端に下がるに違いないんだが、本来換気できていない、全通もしていないトンネル(深い横穴)に入るには、手前から換気していき酸欠をチェックしながら奥に入っていくのが普通。1000mを超える長い上り勾配で行き止まりの穴であれば数日前から換気するくらい考慮するはず。くしくも救助の際、もっとも難航したのが換気であったわけだし。
また、こういう場所では酸欠だけとは限らないので混合検知ができるものを使用するにこしたことはない。
まず何よりも酸欠・硫化水素等作業主任者は置くべき現場であるし、主任者はその手順を踏んだのかがわからない。状況だけから言うと無防備に入っていったように思える。
下請関係も一緒に入っているところを考えると安全衛生責任者等も請負者間できちんと機能していたか不明。
それに中断工事の再開であれば災害防止協議会等を開催する、リスクアセスメントを見直す、などなど事前におこなうことが必要なんだけど…
…と、ここまで書いたけど。
今後事実が明らかになってくるだろうけど、私も業種は違うが監理技術者であり、酸欠・硫化水素作業主任者であり、職長/安全衛生責任者を教育するRSTという立場なので、今回の事故は決して他人事ではないと思う。
書いたのは (´▽`)そると at 22:50│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。